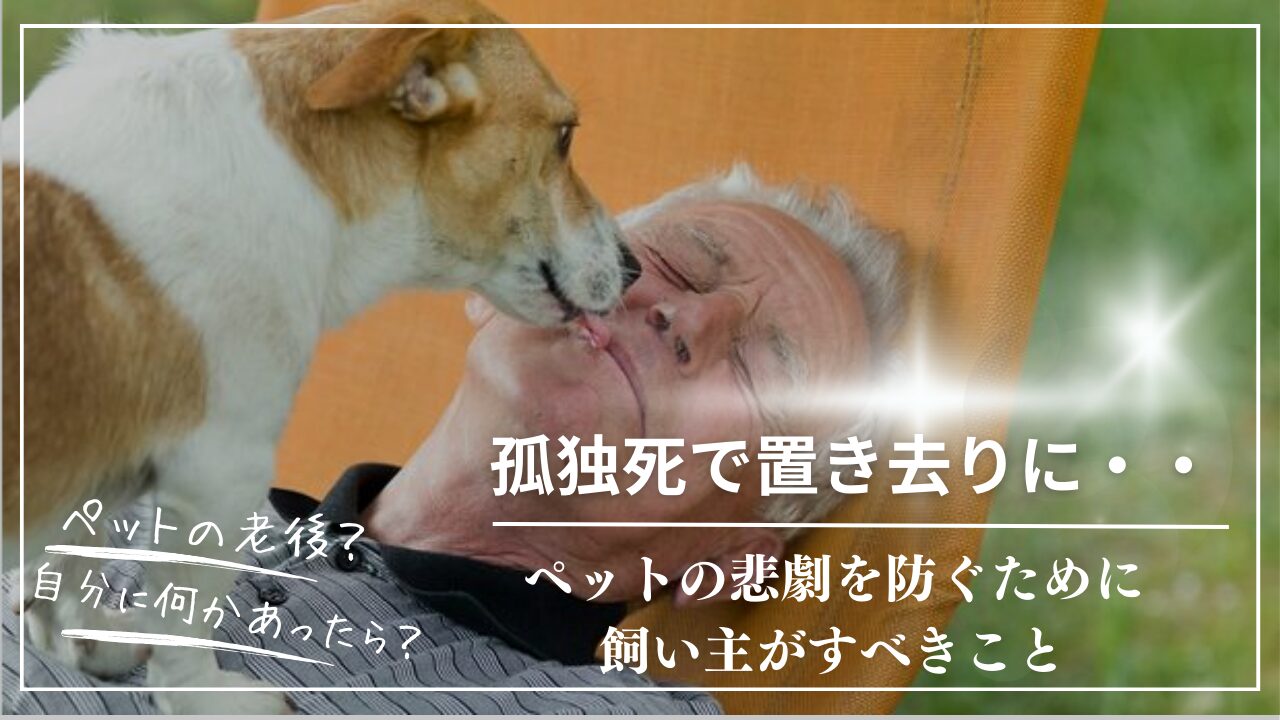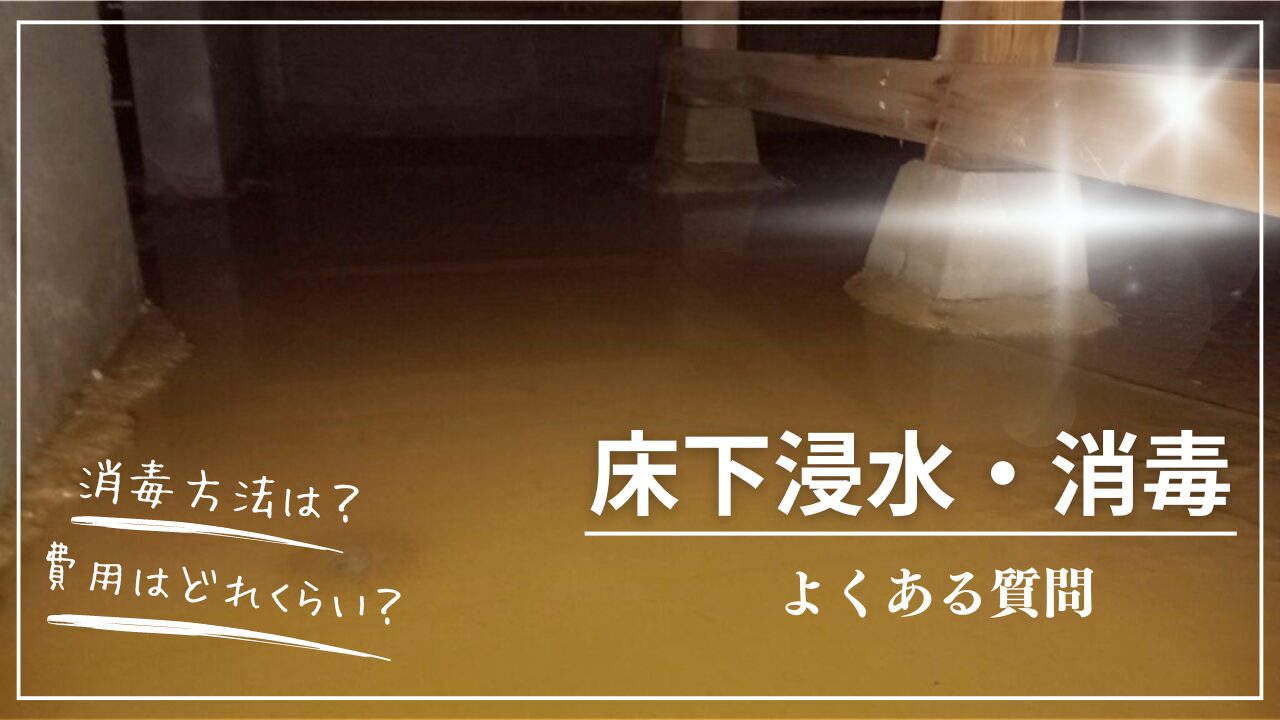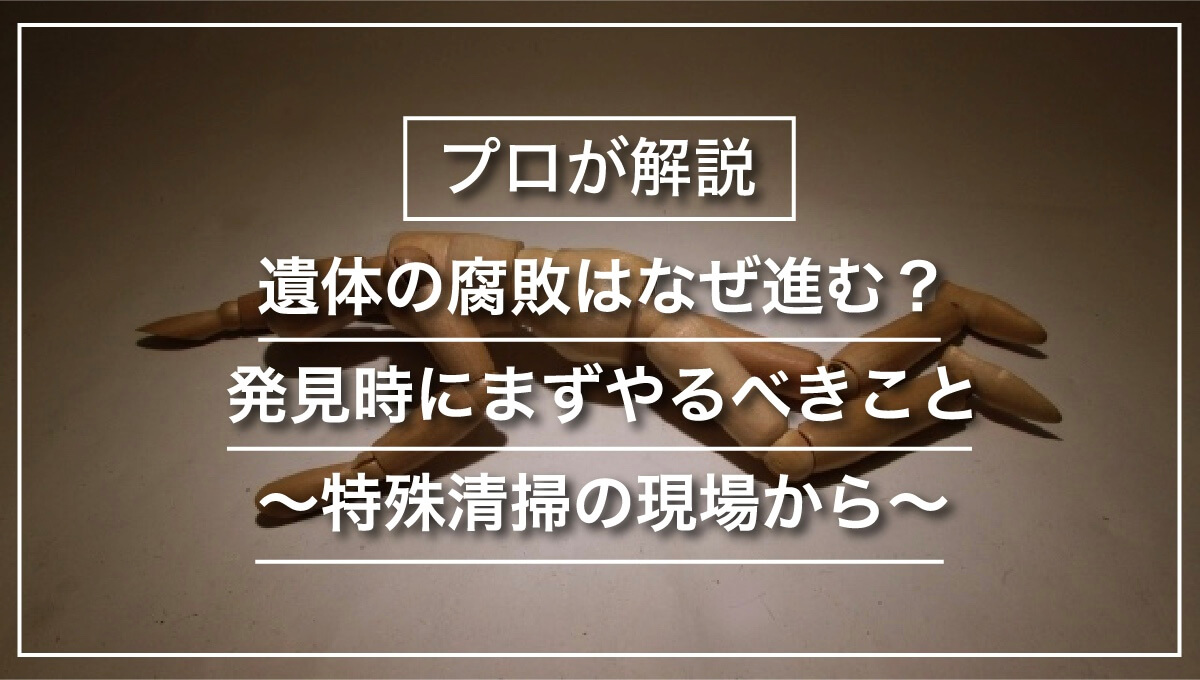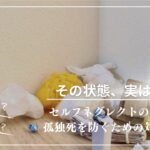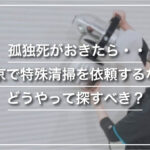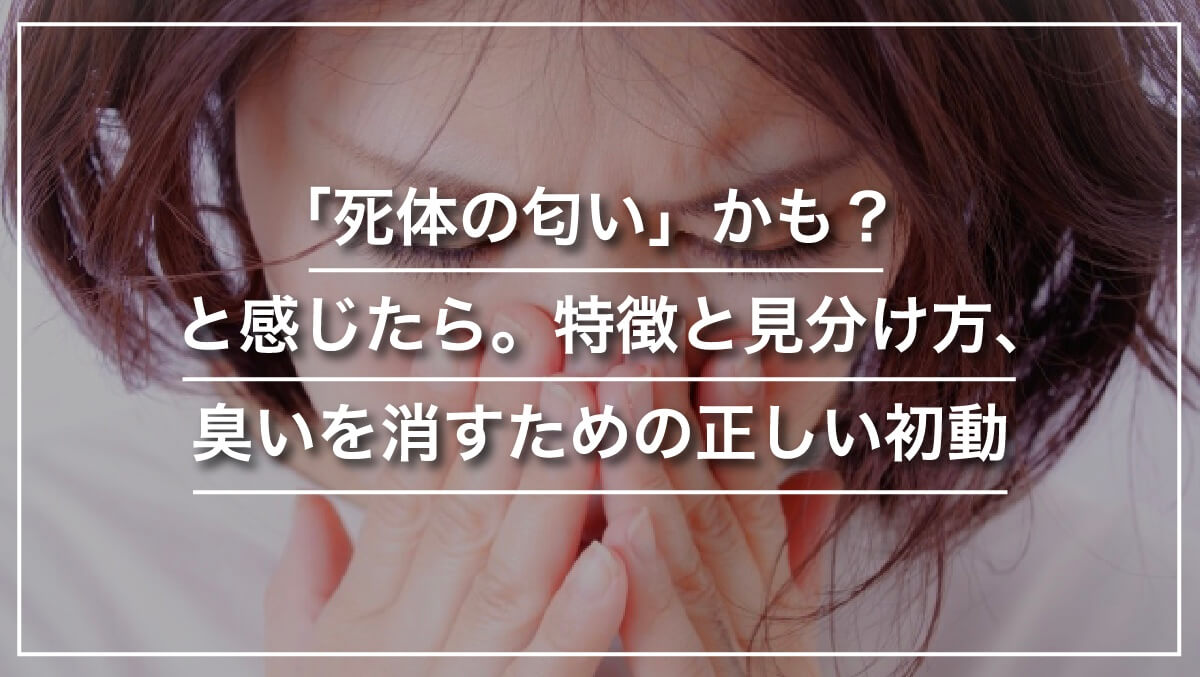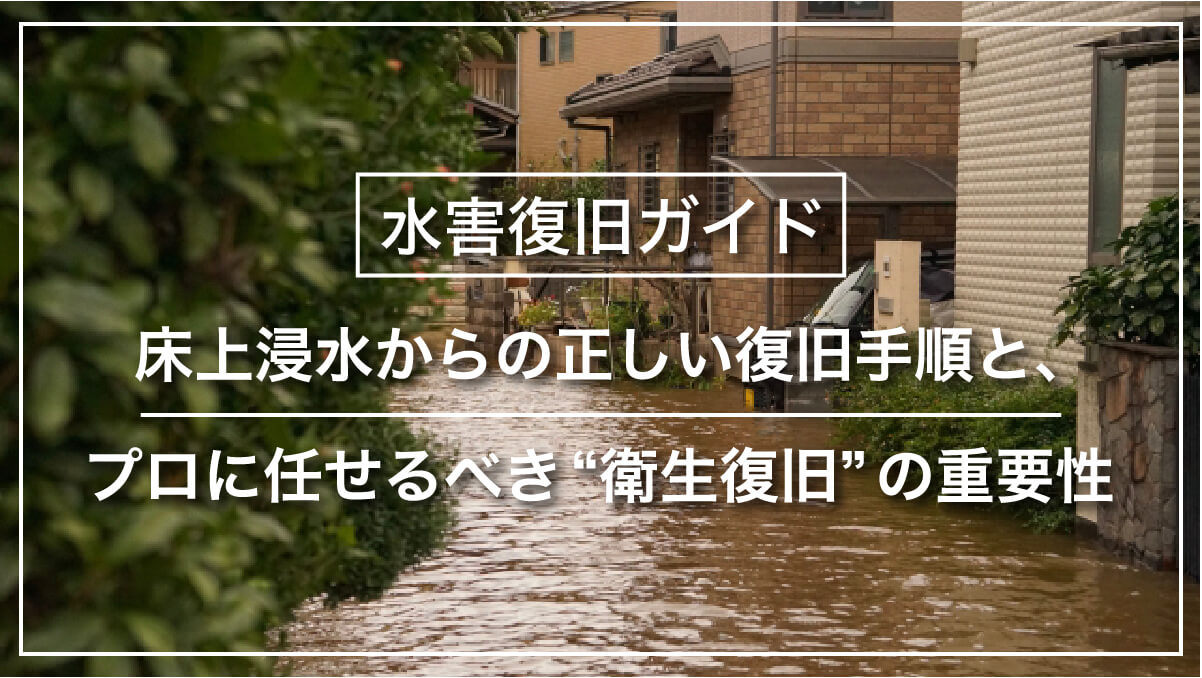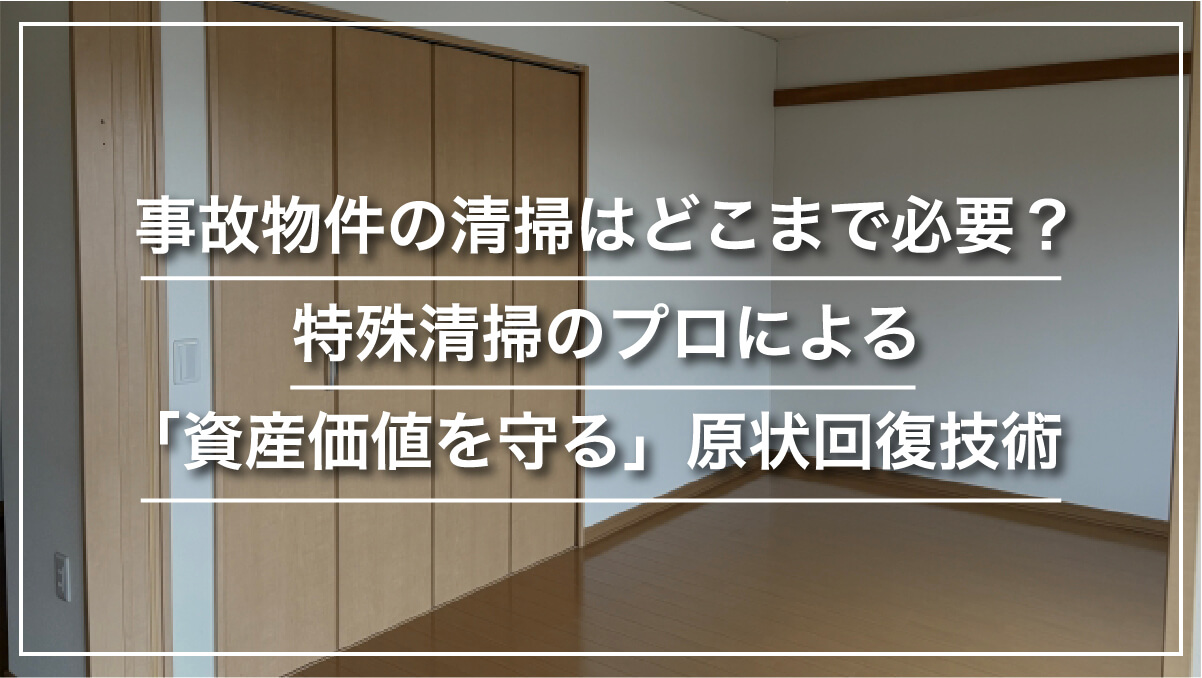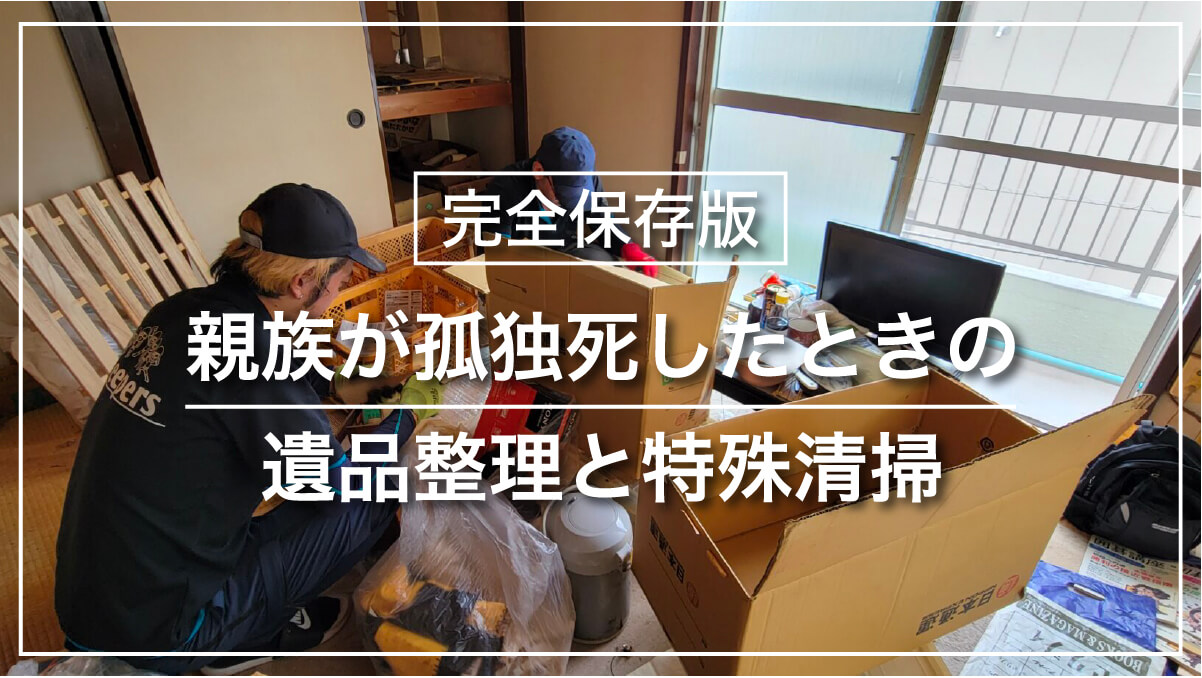狭いケージの中で、糞尿にまみれた床に身を寄せ合いながら、衰弱した猫たちは静かに息を潜めていました。
その隣には、すでに命を落とした仲間の亡骸が、毛と骨だけになって横たわっていたのです。
私たちSweepersが特殊清掃に入ったその施設は、猫の保護を目的とした動物愛護団体の拠点でした。
本来なら、保護された猫たちは安心できる環境で暮らし、新しい里親のもとへと旅立つはずです。
しかし、現場で私たちが目にしたのは、「保護」という言葉からはほど遠い、命の尊厳が失われた空間でした。
ケージの中には、排泄物が溜まり、食器には腐ったフードの残骸。
壁には毛がこびりつき、空気はアンモニア臭と腐敗臭に満ち、ハエが飛び交っていました。
猫たちは極度のストレスと栄養不足で衰弱し、目ヤニで塞がった目、毛玉だらけの被毛、治療されない傷口が痛々しく残されていました。
この施設は、善意から始まった活動の末路でした。
「殺処分ゼロ」を掲げ、行き場のない命を引き受け続けた結果、資金も人手も限界を超え、飼育環境は崩壊。
誰にも助けを求められず、誰にも気づかれず、猫たちは“保護された先”で命を落としていったのです。
このコラムでは、私たちSweepersが実際に清掃に入った「多頭飼育崩壊」の現場をもとに、動物愛護団体が抱える構造的な課題と、善意だけでは乗り越えられない現実を率直にお伝えします。
そして、こうした悲劇を繰り返さないために、私たちが提供できる「環境のリセット」という支援の形についてもご紹介します。
目次
多頭飼育崩壊の現場で見た“保護の限界”

糞尿と毛にまみれたケージ——猫たちの暮らしとは呼べない空間
私たちSweepersが清掃に入ったその施設は、猫の保護を目的としたとある動物愛護団体の拠点でした。
けれど、そこに広がっていたのは「保護施設」とは呼べないほど、過酷な環境でした。
建物内に入る前から漂う猫特有のツンとした臭い。
ケージの中には、何日もいや、何か月も掃除されていない排泄物が溜まり、床には毛やゴミが積もっていました。
食器には腐ったフードの残りがこびりつき、壁や天井にまでには毛が貼りついたまま。室内ははアンモニア臭と腐敗臭で満ちていて、ハエが絶え間なくブンブン音を立てて飛び回っていました。
猫たちは、極度のストレスと栄養不足で衰弱し、身を寄せ合いながら静かに耐えているようでした。
本来なら、保護された猫たちは安心できる場所で心身を回復し、新しい里親のもとへと旅立つはずです。
けれど、私たちが見たのは、命を守るはずの場所が、命を追い詰める空間へと変わってしまった姿でした。
放置された亡骸と衰弱する命——「保護」のはずが命を奪う場所に

ケージの隅には、すでに命を落とした猫の亡骸が、毛と骨だけになって横たわっていました。1匹2匹ではなく数十匹の猫の白骨化した亡骸やまだ白骨化していない腐敗したもの・・
そのすぐそばで、衰弱した猫たちが身を寄せ合い、静かに息を潜めていたのです。
仲間の死を目の前にしながら、誰にも気づかれず、誰にも助けられず、ただ生き延びようとしているように見えました。なかには人間に対して警戒心が強く威嚇してくる猫もいました。
この状況は、決して悪意から生まれたものではありません。
むしろ、動物を救いたいという純粋な善意が、限界を超えてしまったときに起こる悲劇なのだと感じます。
私たちは清掃のプロとして、目に見える汚れや臭いを取り除くことが仕事です。
けれど、この現場では、目に見えるもの以上に、目に見えない“苦しみ”が空間全体に染みついているように感じたのです。
臭気・害虫・衛生崩壊——清掃のプロが見た“SOSのサイン”
清掃に入った瞬間、私たちは空気の重さに息を呑みました。
鼻を刺すようなアンモニア臭、腐敗した猫の亡骸やフードや排泄物が混ざった強烈な悪臭。
その空間に一歩足を踏み入れただけで、目がしみ、喉が焼けるような感覚に襲われました。
無数のハエが群がり私たちが室内に入るといっせいに飛び回ります、壁や天井にはクモの巣が張り巡らされそれらに猫の毛が絡まり、ケージの隙間にはフードのカスや毛、排泄物がびっしりと詰まっていました。
排泄物は乾いて層になり、踏むと粉塵が舞い上がる場所、猫の尿と混じりぐちゃぐちゃしている場所。
こうした環境は、猫たちの健康を著しく損なうだけでなく、感染症や皮膚病、呼吸器系の疾患を引き起こす原因にもなります。
しかし、影響を受けていたのは猫たちだけではありません。
この空間で日々世話をしていた人たちの健康も、確実に蝕まれていたはずです。
長時間にわたって悪臭の中で世話を続けることは、頭痛や吐き気、慢性的なストレスや疲労感を蓄積させます。
実際、現場には簡易ベッドが置かれ、そこに倒れ込むように休んでいた形跡がありました。
「休憩中」と書かれた手書きの紙が貼られたその場所は、限界まで追い詰められた人の姿を物語っているようでした。
私たちSweepersは、こうした“SOSのサイン”を見逃しません。
臭いの種類、汚れの層、害虫の発生状況——それらは、現場の過去と現在を物語る「痕跡」であり、そこにいた命たちの叫びでもあります。
このような環境が放置されてしまう背景には、「助けを求める余裕すらなかった」という現実があるのかもしれません。
だからこそ、私たちは清掃のプロとして、ただ汚れを取り除くだけでなく、そこにあった苦しみや孤立にも目を向けながら、空間を“リセット”していく必要があると感じています。
なぜ善意が悲劇を生むのか?——多頭飼育崩壊の構造的背景
「殺処分ゼロ」の理想と現実のギャップ
「殺処分ゼロ」——この言葉には、命を守りたいという強い願いが込められています。
多くの動物愛護団体は、この理想を掲げ、行き場を失った猫たちを積極的に保護しています。
行政の施設では収容しきれない、あるいは殺処分の対象となってしまう命を救いたい——その思いが、活動の原動力になっていることは間違いありません。
けれど、現場に立つと、その理想と現実の間には、想像以上に深い溝があることに気づかされます。
保護された猫たちが増え続ける一方で、飼育スペースや人手、資金は限られており、すべての命に十分なケアを届けることが難しくなっていくのです。
善意から始まった活動が、やがて限界を超え、命を守るはずの場所が命を苦しめる空間へと変わってしまう——それが、多頭飼育崩壊の根底にある構造的な問題です。
断れないSOSと終わらない保護の連鎖
「この子を助けてください」「もう飼えなくなってしまったんです」
動物愛護団体には、日々こうしたSOSが寄せられています。
高齢の猫、病気を抱えた子、虐待の経験がある子——行政では対応が難しいケースほど、団体が手を差し伸べることになります。
目の前で助けを求める命に「ノー」と言うことは、動物を愛する人ほど難しいものです。
その優しさと責任感が、次の命を引き受ける原動力になっている一方で、保護の連鎖が続くことで、気づかぬうちに飼育環境が限界を迎えてしまうこともあります。
私たちSweepersも、孤独死や飼育困難な現場で保護された猫を、信頼できる団体に託し、里親探しをお手伝いすることがあります。
そのたびに感じるのは、「助けたい」という気持ちがどれほど強くても、現実には支援の枠組みや環境が整っていなければ、継続的な保護は難しくなってしまうということです。
これは、誰かの責任を問う話ではありません。
むしろ、善意の活動が持続可能であるために、社会全体で支え合う仕組みが必要だと、現場に立つたびに痛感しています。
資金・人手・スペースの限界が引き起こす崩壊

猫たちを保護するということは、単に食べ物と寝床を用意するだけではありません。
毎日の排泄物の処理、清潔な環境の維持、健康状態の管理、医療ケア、そして心のケア——すべてが必要です。
特に、心身に問題を抱えた猫のケアには、専門的な知識と時間、そして費用がかかります。
医療費、フード代、猫砂、光熱費——それらは毎日積み重なり、団体の運営を圧迫していきます。
人手もまた深刻な課題です。
ボランティアは入れ替わり立ち替わりで協力してくれることもありますが、長期的に重労働を担う人材は限られています。
運営者が一人で何十匹もの猫の世話をしているケースも珍しくありません。
こうして、資金も人手もスペースも限界を超えたとき、飼育環境は崩壊し、猫たちの命が危険にさらされるのです。
それは、誰かの悪意ではなく、善意が抱えきれなくなった結果として、静かに起こってしまう悲劇なのではないでしょうか。
清掃現場から見えた“声なきSOS”——運営者の孤立と疲弊
支援を求められなかった団体の実情
私たちが清掃に入った施設の中には、すでに運営者の姿が見えなくなってしまった場所もありました。
大家さんからの依頼で作業を行った賃貸戸建て住宅は庭先にもケージや猫のフードのごみ、寄付されたのか大量の猫砂も無残に雨に濡れていました。動物愛護団体に部屋を貸したまま夜逃げされ室内もひどい状態・・
玄関先には「動物愛護団体」の旗が破けた状態で風に揺れ、郵便受けには未開封の支援チラシや寄付の案内が積もったまま。
それは、愛護団体が助けを求めようとした痕跡のようにも見えました。けれど、その声が届かず、時間だけが静かに流れていたような印象を受けました。
「この子たちを守れるのは自分しかいない」
「他の団体に迷惑をかけたくない」
「支援を求めたら、無能だと思われるかもしれない」
そんな思いが、運営者の中にあったのかもしれません。
現場に立つと、そうした葛藤や責任感の重さが、空間全体に染みついているように感じられることがあります。
善意と使命感が強い人ほど、問題を外に出すことをためらい、誰にも言えないまま、ひとりで抱え込んでしまうこともあるのかもしれません。
私たちは、多頭飼育崩壊の現場で、そうした“声なきSOS”のような空気を、何度も肌で感じてきました。
ボランティアの限界とバーンアウトの連鎖
動物の世話は、想像以上に体力と気力を必要とする作業です。
毎日の排泄物の処理、ケージの清掃、給餌・給水、医療ケア、そして心のケア——それらを少人数でこなすことは、並大抵のことではありません。
現場には、疲れ果てたように置かれた簡易ベッドや、「休憩中」と書かれた手書きの紙が残されていました。
それを見たとき、私は、ここで暮らす猫たちだけでなく、世話をする人たちもまた限界に近づいていたのではないかと感じました。
ボランティアの方々は、時間や体力を惜しまず活動されていて、本当に頭が下がる思いです。
ただ、現場に立つと、継続的な支援の難しさや、担い手の入れ替わりによって負担が偏ってしまうこともあるのではないか——そんなことを考えさせられます。
猫たちのケアが行き届かなくなるのは、誰かの怠慢ではなく、支える人の数や仕組みが足りていないからかもしれません。
私たちは清掃の立場から、そうした“支える側の疲弊”にも目を向ける必要があると感じています。
環境省|多頭飼育対策ガイドライン
多頭飼育崩壊は、飼育環境だけでなく人の孤立や福祉とも深く関係しています。
環境省が公表した多頭飼育対策ガイドラインでも、社会福祉と動物愛護の連携の重要性が強調されています。
「善意の強要」が生むプレッシャーと沈黙
「殺処分ゼロを目指しているんだから、この子も引き取ってほしい」
「困っている動物がいるのに、なぜ助けてくれないの?」
こうした言葉は、動物を思う気持ちから発せられるものだと思います。
けれど、現場に立つと、それが団体の方々にとって大きなプレッシャーになっているのではないか——そんな空気を感じることがあります。
猫のキャリーケースと一緒に置かれていた「メッセージカード」。
「どうかこの子を助けてください」と書かれたその一文は、誰かの切実な願いであると同時に、団体に託された重責のようにも見えました。
支援のつもりで差し出された言葉や行動が、時に“丸投げ”のように受け取られてしまうこともあるのかもしれません。
それが、団体の方々の沈黙や孤立につながってしまうことがあるのではないか——そんなことを、現場で感じることがあります。
私たちは、清掃のプロとして、物理的な汚れだけでなく、そこに染みついた感情や葛藤にも寄り添いながら、空間を整えていきたいと思っています。
そして、こうした“声なきSOS”が届く社会であってほしいと、心から願っています。
🐾保護猫たちが安心して暮らせる空間を整えるために
私たちSweepersは、ただ汚れを落とすだけの特殊清掃業者ではありません。
特殊清掃専門業者ならではの技術を活かし、目に見える汚れだけでなく、臭気や菌、体液などの“痕跡”をしっかり除去することができます。
動物の排泄物や腐敗臭は、通常の清掃では取りきれないことが多く、壁や床材に染み込んでしまうこともあります。
私たちは、専用の薬剤と機材を使い、空間全体に残る“記憶”のような臭いや汚れを、徹底的に取り除いていきます。
使用する薬剤は、猫や犬などのペットがいても安心して使えるものを選定しています。保護された動物たちが、清掃後も安全に過ごせるよう、成分や残留リスクにも細心の注意を払っています。
私たちが目指しているのは、ただ清潔にすることではなく、動物たちが心身ともに落ち着いて暮らせる環境を“リセット”すること。
そこにあった命に敬意を払いながら、次の命が安心して過ごせる空間を整える——それが、私たちSweepersの役割だと感じています。
空間を整えることで、命の居場所をもう一度つくる

私たちSweepersは、特殊清掃だけでなく、必要に応じて内装の解体や原状回復工事まで一括して対応できます。
壁紙や床材の張り替え、設備の交換などを通じて、空間を「すぐに住める状態」へと整えることが可能です。
動物愛護団体の施設であれば、保護猫たちが安心して過ごせる環境に。
個人宅であれば、次の入居者が心地よく暮らせる空間に。
私たちは、衛生と安全を確保するだけでなく、「再出発できる場所」をつくることを目指しています。
また、清掃の過程で亡くなった動物の遺骨が見つかった場合には、飼い主や団体に代わって、提携するペット霊園での永代供養を手配しています。
命の痕跡を丁寧に扱い、最後まで敬意を込めて送り出すことも、私たちの大切な役割のひとつです。
「片付ける」ことは、過去を整理するだけでなく、未来に向けて歩き出す準備でもある——そう感じながら、私たちは一つひとつの作業に向き合っています。
悲劇を繰り返さないために——社会全体でできること
善意を支える“仕組み”が必要です
多頭飼育崩壊の現場に立つたびに感じるのは、「善意だけでは守りきれない命がある」ということ。
動物を救いたいという気持ちは尊いものですが、それを継続的に支える仕組みがなければ、やがて限界を迎えてしまいます。
保護団体が安心して活動できるようにするには、資金面だけでなく、人的支援や情報共有、行政との連携など、さまざまな支えが必要です。
「助けたい」という気持ちが、孤立や疲弊につながらないように——そのためには、社会全体で支え合う土台づくりが欠かせません。
私たちSweepersも、清掃業者という立場から里親探しや毛布、タオルの寄付などを行っていますが、今以上にそうした支援の一端を担えたらと思っております。
どうぶつ基金|多頭飼育崩壊救済支援
多頭飼育崩壊の現場では、無料不妊手術などの支援を行う団体もあります。
たとえば、どうぶつ基金の多頭飼育救済支援では、行政と連携しながら現場の命を守る取り組みが行われています。
個人にできること——知る・広める・寄り添う
「自分には何もできない」と感じる方もいるかもしれません。
けれど、まずは“知ること”が大きな一歩です。
多頭飼育崩壊の背景や、保護団体の活動、現場で起きていることを知るだけでも、社会の空気は少しずつ変わっていきます。
SNSで情報を広める、信頼できる団体に寄付する、保護猫の里親になる、ボランティアに参加する——どれも立派な支援です。
そして何より、「責める」のではなく「寄り添う」姿勢が、現場で活動する人たちの心の支えになります。
私たちが清掃に入るとき、運営者の方が「誰にも言えなかったことを、ようやく話せました」と涙を流されることがあります。
その瞬間に、空間だけでなく、心も少しずつ整っていくのを感じるのです。
命を守る活動が、孤立しない社会へ

動物を守る活動は、決して一部の人だけが担うものではありません。
行政、企業、地域、そして個人——それぞれが少しずつ関わることで、命を守る輪は広がっていきます。
たとえば、企業が衛生用品やフードを寄付すること。
行政が情報提供や一時保護の仕組みを整えること。
地域が団体の活動を理解し、見守ること。
そして、私たちのような清掃業者が、環境の再生を支えること。
それぞれの立場でできることを持ち寄れば、善意が孤立することなく、持続可能な支援へとつながっていくはずです。
私たちは、命の痕跡に敬意を払いながら、空間を整える仕事を通じて、そんな社会の一員でありたいと願っています。
今回の記事はこれまでの現場経験をもとに私個人的な思いを綴ってみました。罪なき小さな命が失われることがないよう願っております。
私たちで解決できることがあればぜひご連絡してください。


 2025.10.25
2025.10.25