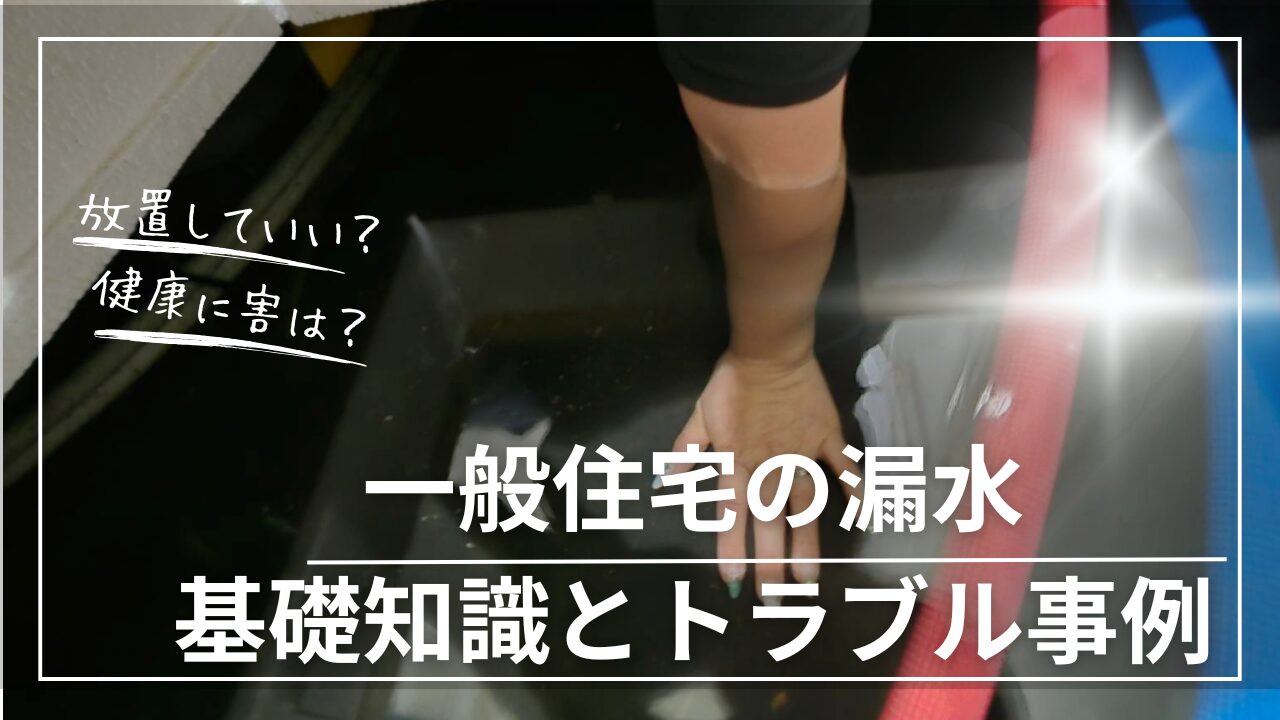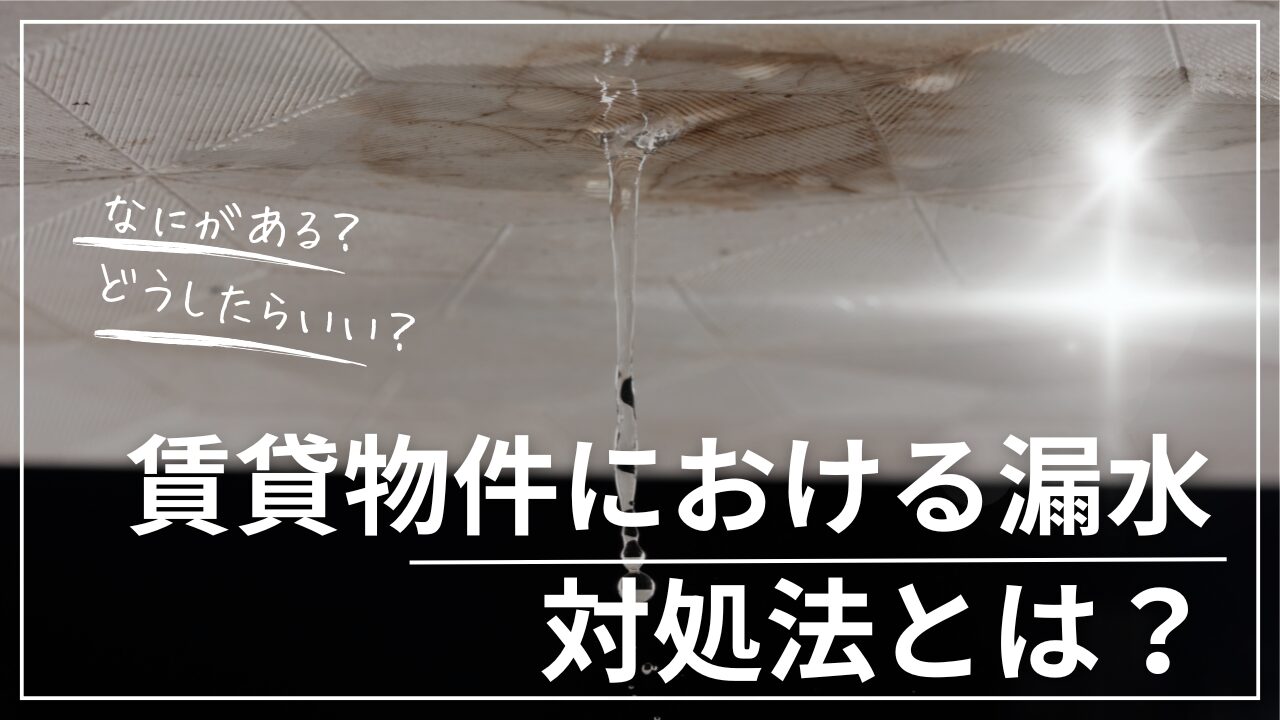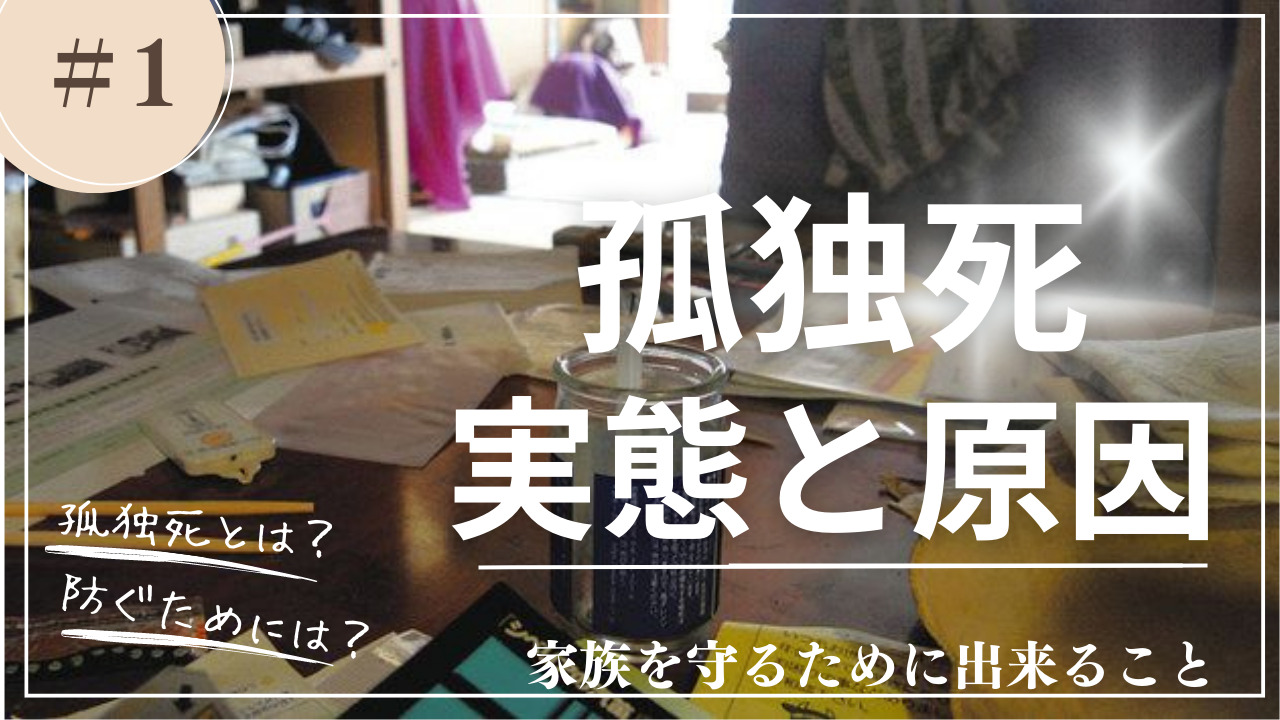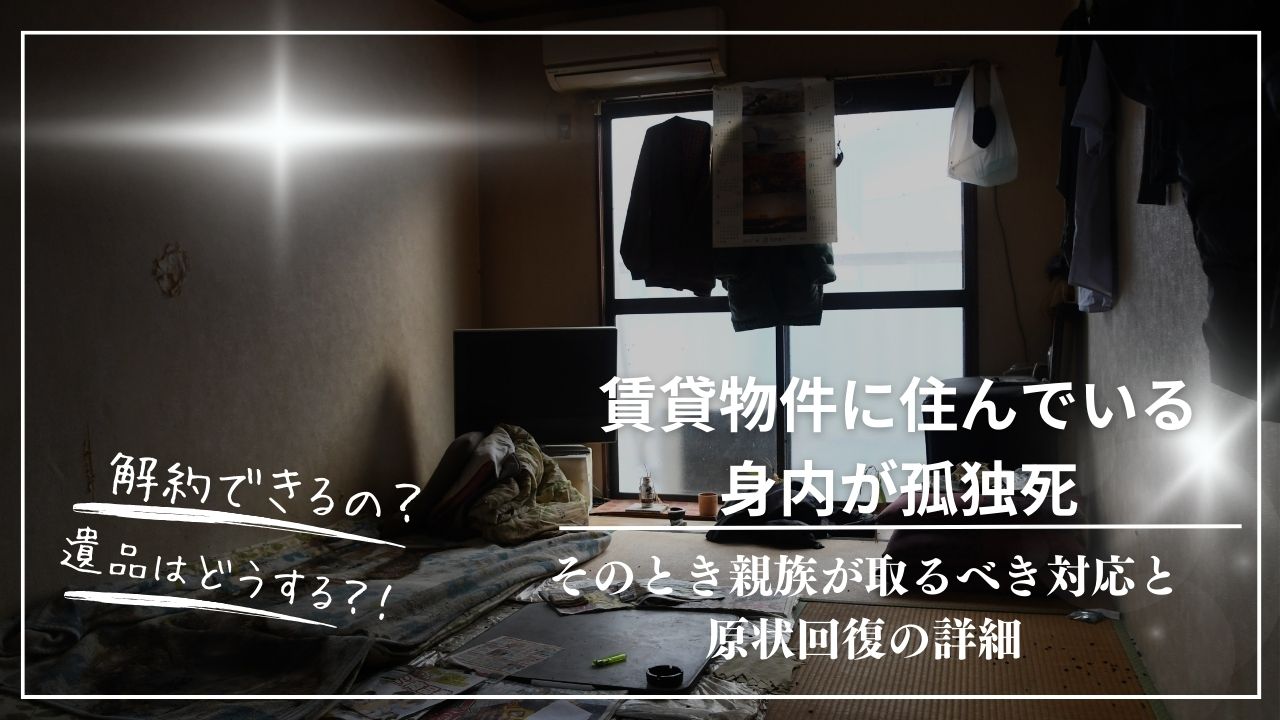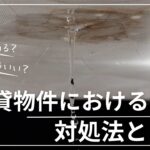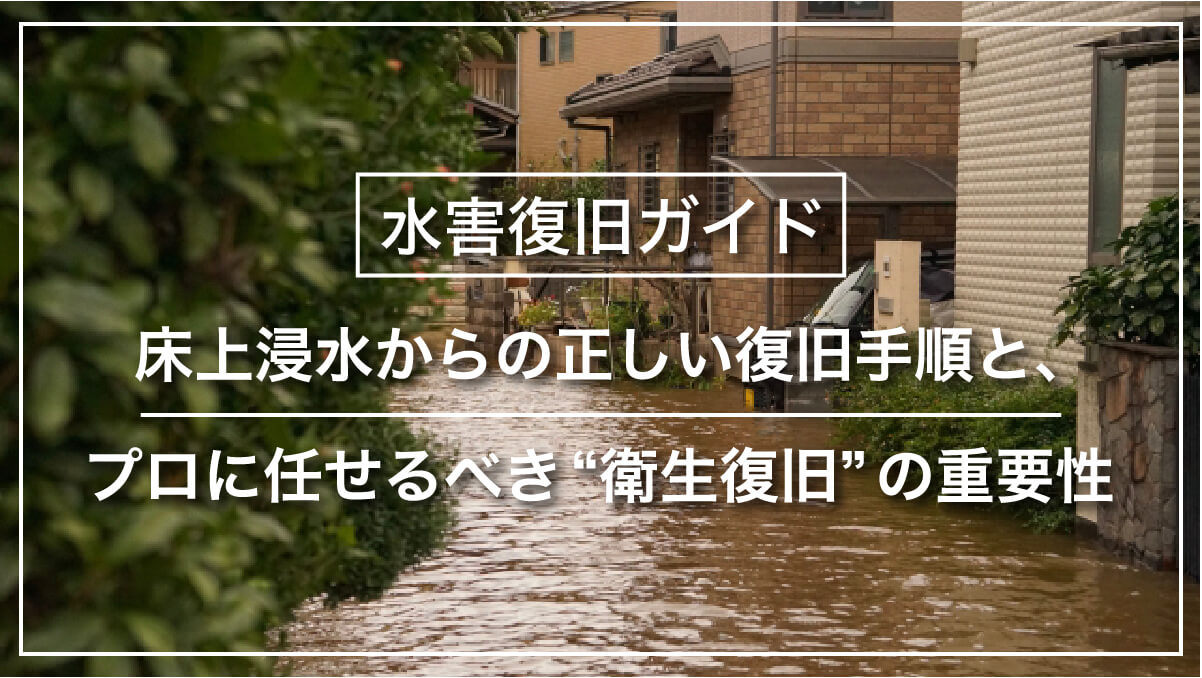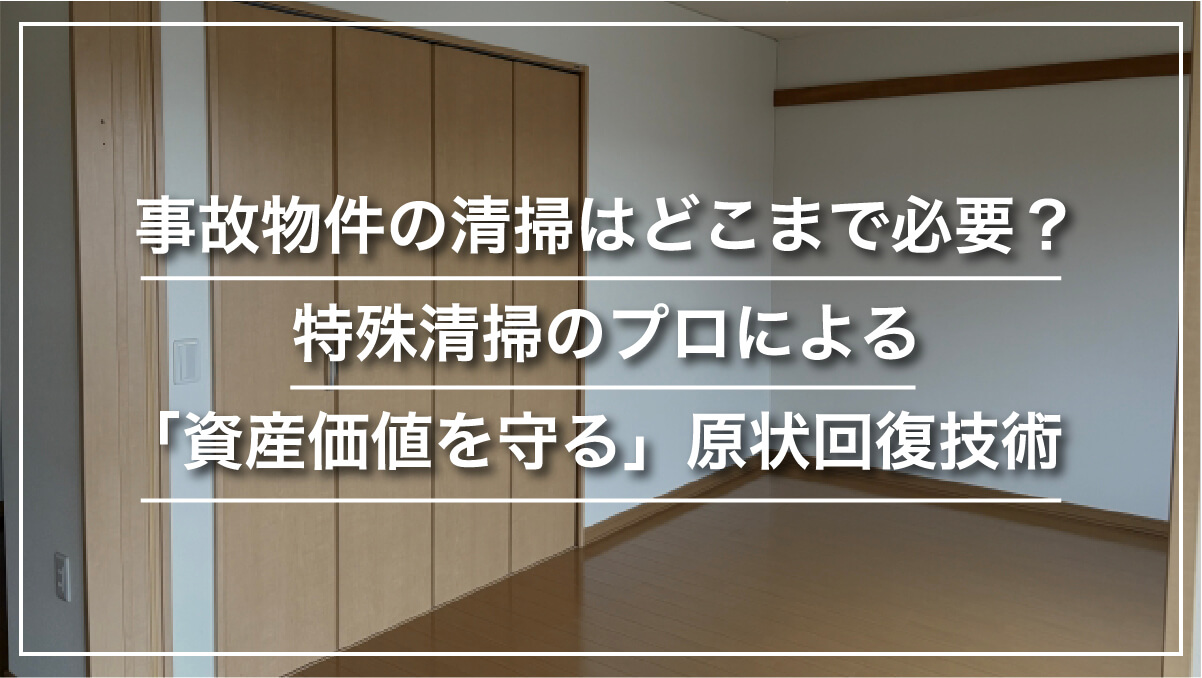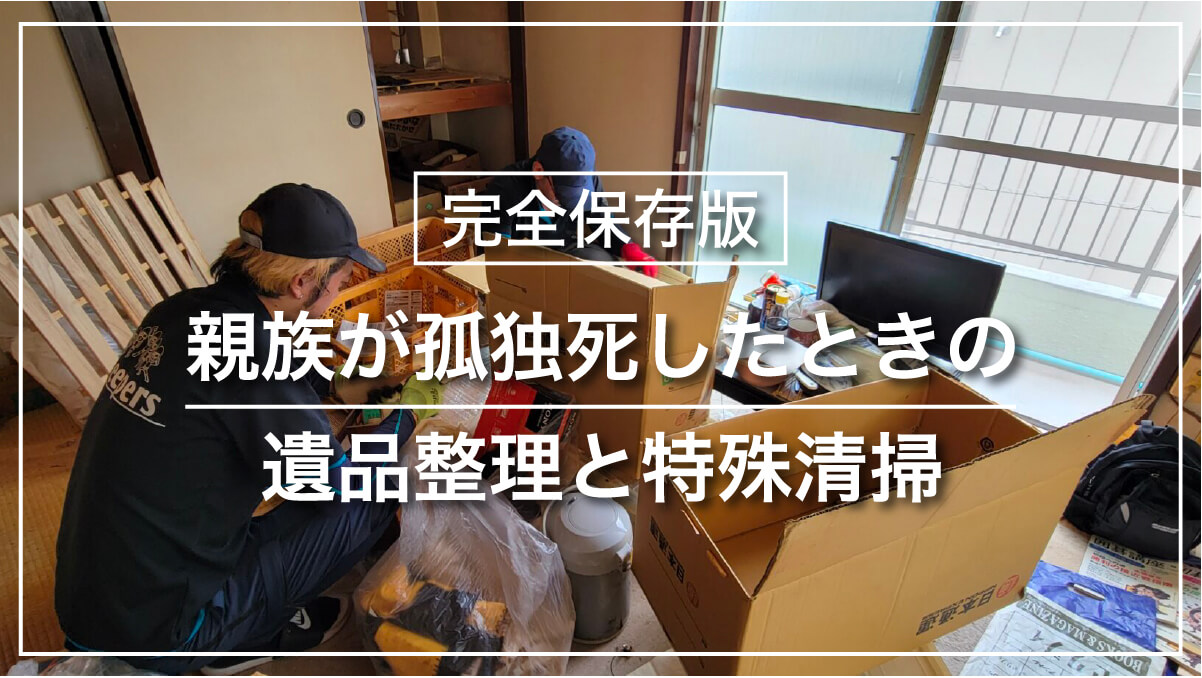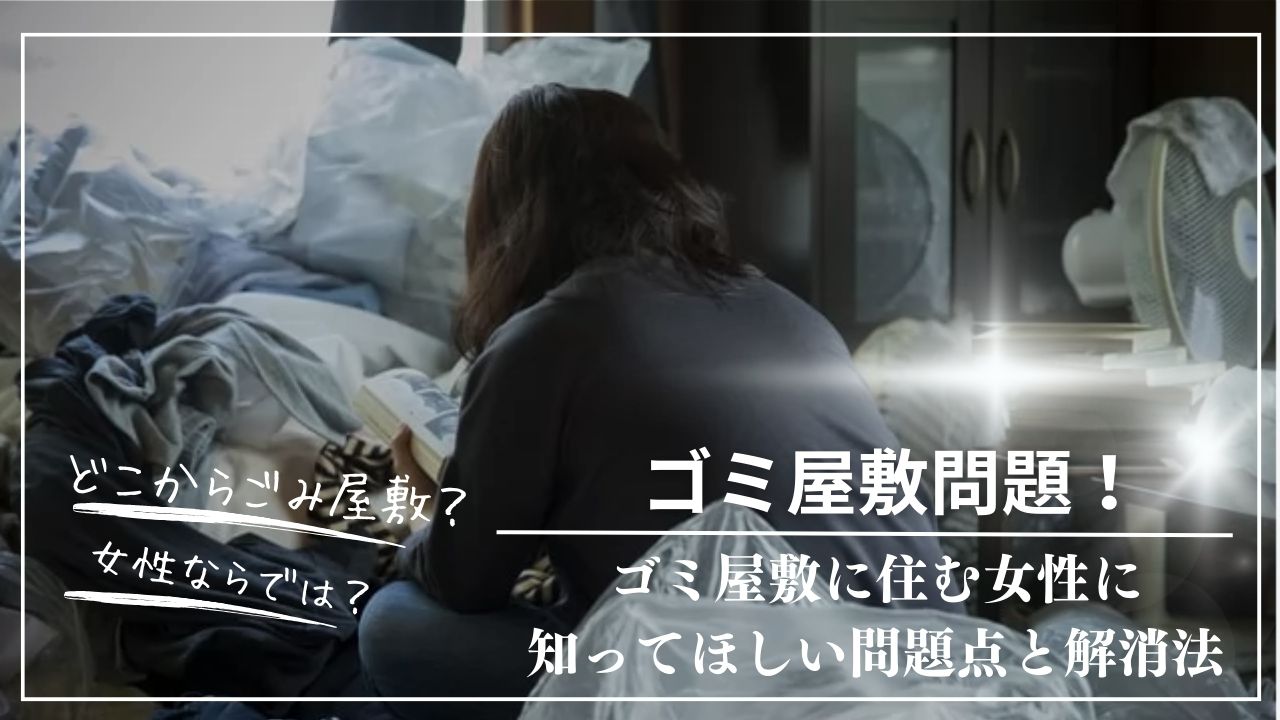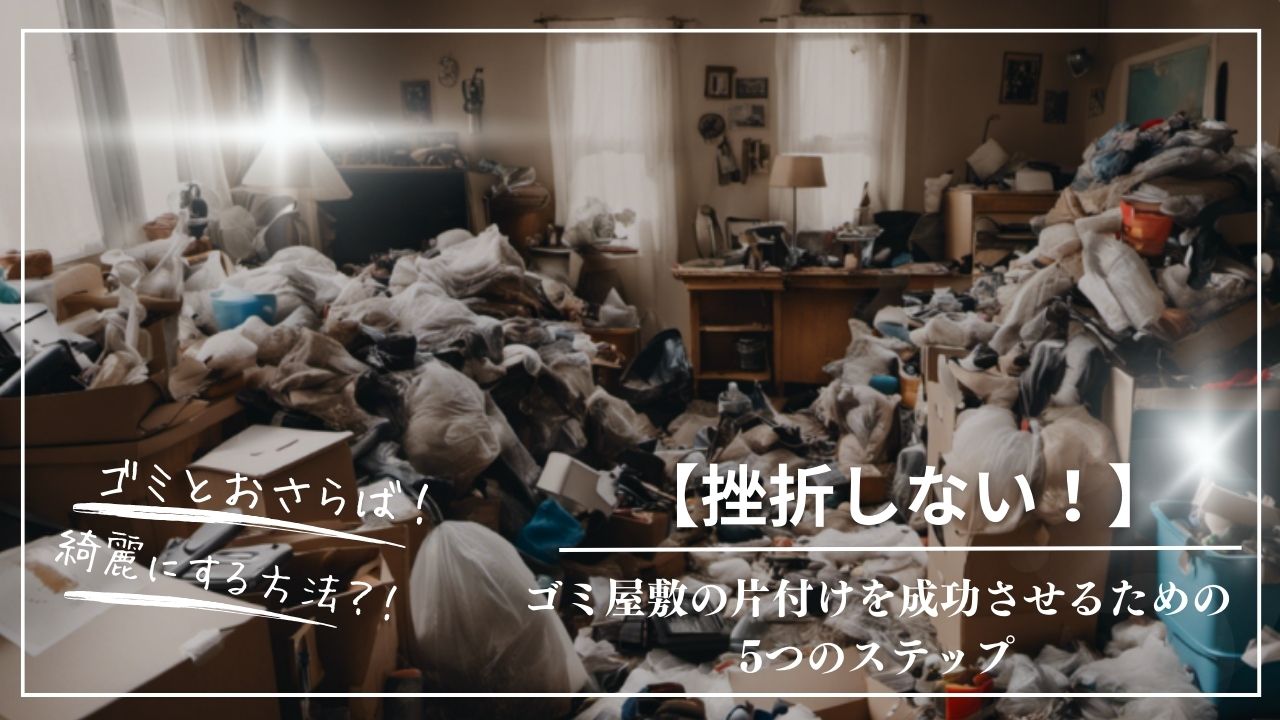お子様の健康、大丈夫ですか?
近年、住宅におけるカビ問題は深刻化しており、健康被害や建物の劣化など様々な問題を引き起こしています。特に、免疫力や抵抗力が未熟な乳幼児は、カビの影響を受けやすく、深刻な健康被害につながる可能性があります。
この記事では、子供のいる家庭向けの住宅カビ問題について、わかりやすく解説します。
今回は生活していると気づくことが難しい床下のカビについて説明していくのでご自宅の床下点検口から床下の確認をしてみてくださいね!!
目次
カビが子供に与える影響
- アレルギーや喘息: カビを吸い込むことで、アレルギー性鼻炎、気管支喘息などの呼吸器疾患を引き起こす可能性があります。
- アトピー性皮膚炎の悪化: カビはアトピー性皮膚炎の症状を悪化させる因子の一つと考えられています。
- その他: カビによっては、目や鼻、喉などの粘膜に炎症を起こしたり、免疫力低下を引き起こしたりする可能性があります。
大人に比べ子供や乳幼児がカビに反応しやすい理由

1. 免疫力・抵抗力が未熟
乳幼児は、大人に比べて免疫力や抵抗力が未熟です。そのため、カビなどの有害物質の影響を受けやすく、アレルギー反応を起こしやすい傾向があります。
2. 呼吸量が多い
乳幼児は、大人に比べて体重あたりの呼吸量が多いため、より多くのカビ胞子を吸い込むことになります。その結果、カビに対するアレルギー反応を起こしやすいと考えられています。
3. 床を這ったり、口に入れたりする
乳幼児は、床を這ったり、おもちゃや物を口に入れたりする行動が一般的です。そのため、床や家具などに付着したカビ胞子を吸い込んだり、取り込んだりするリスクが高くなります。
4. 気道が狭い
乳幼児の気道は、大人に比べて狭いため、カビ胞子などの異物が引っかかりやすく、炎症を起こしやすいと考えられています。
5. 皮膚が薄い
乳幼児の皮膚は、大人に比べて薄いため、カビなどの刺激を受けやすく、アレルギー反応を起こしやすいと考えられています。
近年の住宅カビ問題:深刻化する原因
近年、住宅におけるカビ問題は深刻化しており、健康被害や建物の劣化など様々な問題を引き起こしています。床下浸水の復旧作業中にカビを発見するケースや原因不明の消臭のご依頼、その原因がカビの臭いだったということもあるのです。
カビ問題が深刻化する原因
- 高気密・高断熱住宅の普及: 近年、省エネ性能の高い高気密・高断熱住宅が普及していますが、こうした住宅は換気が不足しやすく、湿気が溜まりやすいため、カビが発生しやすい環境となります。
- 温暖化による湿度上昇: 地球温暖化の影響により、近年は湿度が高くなる傾向があります。湿度が高いとカビが発生しやすくなるため、住宅カビ問題が深刻化していると考えられます。
- 異常気象による水害被害:ゲリラ豪雨や線状降水帯など、数十年前は聞かなかった大雨の影響により住宅への浸水被害が多く発生するようになり、住宅へのカビ問題が身近に感じられるようになった方が多くいるように感じます。
- 化学物質過敏症やアレルギー疾患の増加: 近年、化学物質過敏症やアレルギー疾患の人が増加しており、カビに対する感受性も高くなっていると考えられます。
目に見えるカビは対処がしやすいので今回は、日常生活では気づかない場所のカビについて詳しく見ていきましょう。
床下にカビが生えやすい家の特徴
床下は、目に見えない部分であり、カビが生えやすい環境が整っていることが多い場所です。
そもそもカビ菌とは、高温多湿の環境下で発生し、繁殖します。
具体的には、温度15℃から30℃(特に20℃から28℃)湿度60%から80%以上の範囲がカビの発生に適しています。
また、カビの主な主食となるのが、有機物(土、ほこりなど)です。
カビは、この条件が揃うと発生し、急速に増殖していきます。
では、実際にカビが発生しやすい家の特徴とはどのようなものなのでしょうか?
1.建物の立地

「新築に引っ越してすぐにカビが発生した」、というケースもよくあることです。
その場合、家を建てた場所に問題があるケースが考えられます。
カビが発生しやすい立地については、以下の通りです。
- 埋立地の上に家が建っている
- 川沿いや沼地、田んぼなどの近くに家が建っている
- 家の周辺に自然が多い
埋立地や川沿いの近くは湿度が高くなりやすく、「カビ菌」は土壌に多く生存しているため、自然豊かな場所の近くはカビの胞子も多くなります。
そもそも、カビの発生しにくいエリアを選んで家を建てるというのも可能ですが、
すでに家が建っている場合は、しっかり対策をしてカビを防ぐようにするしかないといえます。
2.水害による浸水被害に遭った

台風の大雨などにより、付近の河川や用水路が氾濫し、溢れ出た水が床下、
または、床上に流れ込んでしまった(床下浸水・床上浸水)状態の場合は、カビが発生する確率が非常に高いといえるでしょう。
もちろん、先ほどご説明したように、高温多湿の環境下になてしまうというのも、発生原因の一つですが、基本的に、多くの河川や用水路には数多くの細菌が潜んでいます。
その中に、カビの元となる菌(カビ菌)も含まれており、それが水と共に流れ着き、その場所で繁殖していくという可能性があるのです。
このような、いわゆる自然災害的要因は、人間の手ではどうすることもできません。
そのため、しっかりと浸水被害後の洗浄消毒を行い、カビ被害を予防していく必要があります。
3.配管の水漏れ

築年数が経過した建物では、給水管や排水管が劣化し、亀裂や繋ぎ目から水漏れが発生することがあります。
特に、排水管は汚れや油脂が溜まりやすく、詰まりや腐食によって水漏れのリスクが高まります。
また、配管の施工不良が見られるケースもあります。こちらは新築時のみならず、リフォーム工事の後で起きることがあり弊社にご依頼がある床下作業の一つです。
施工時に繋ぎ目がしっかりと接着されていなかったり、適切な材料が使用されていなかったりすると、水漏れが発生しやすくなります。
このように、床下の配管から、気づかないうちに水漏れが発生し、長期間湿った状態が続くと、カビが発生しやすくなります。
4.風通しが悪く湿気がこもりやすい

近年は高気密・高断熱の住宅が非常に増えました。
隙間を無くし、断熱材や断熱効果のある窓を採用することで外気の影響を受けにくくなっています。
そのお陰で1年を通して快適に生活できるようになったことは確かです。
快適に過ごせるようになった反面、気密性が高い住宅は空気の入れ替えが行われにくく、湿度が高くなりやすい傾向にあります。
そうなると室内の湿度が上がり、常に高湿度の状態になってしまいます。
その結果、カビが好む条件下となってしまい、カビの発生確率が高くなってしまうという事です。
床下のカビの確認方法
床下は目に見えない場所なので、カビが生えているかどうか確認するのは難しいと感じますよね。
しかし、いくつかの方法で床下の状態を推測することができます。
1. 床下の点検口から確認する
ほとんどの家には、床下に潜るための点検口が設けられています。点検口を開けて、懐中電灯などで床下の様子を観察してみましょう。カビが生えている場合は、黒ずみ、白い綿状のカビ、あるいは緑色のカビなどが目に見えます。
2. 床の状態をチェックする
床が腐ったり、変色したりしていないか確認しましょう。床下でカビが発生していると、床に湿気やカビ臭いが移ることがあります。また、床がフカフカしたり、バネのような感触があったりする場合も、床下にカビが生えている可能性があります。
3. 室内の湿度を測る
床下は室内の湿度よりも高くなりやすい傾向があります。室内の湿度が高い場合は、床下もカビが生えやすい状態と言えます。湿度計を使って、室内の湿度を定期的に測定しましょう。
4. 専門業者に依頼する
床下の状態を自分で確認するのが難しい場合は、専門業者に依頼するのも一つの方法です。専門業者は、専用の機器を使って床下の状態を調査し、カビの有無や発生場所を特定することができます。
床下のカビを放置するとどうなる?
1.シックハウス症候群の原因になることも

※日経クロステック記事引用https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00154/00247/
そもそもシックハウス症候群とは、建材、家具、日用品などから発せられる化学物質やカビ、ダニ、ハウスダストなどが室内に充満し、それを吸い込んだり肌に触れたりすることでさまざまな症状を引き起こす病気のことです。
近年、住宅のカビが原因のシックハウス症候群の事例が増加傾向にあります。
主に換気不足による空気の充満が引き金になっているとされていますが、
実際にシックハウス症候群にかかると以下のような症状が見られます。
- 目がチカチカする
- 鼻水が出る
- 吐き気がする
- 頭痛がする
- 湿疹が出る
前半に記載した通り、特に子どもたちは、大人と比べると、体重あたりの呼吸量と飲食物
の摂食量が多く、体の機能(中枢神経、免疫、消化器系、)は傷つきやすいこと、さらに乳幼児については手を口に入れる行為によって手に付着した物を体内に取り込みやすいことなどのため、大人よりも環境汚染に対し一層の注意が必要です。
また、重症化した場合、日常生活に大きな影響をもたらす可能性があるため、特に免疫力の弱い乳幼児や小児には注意が必要です。
2.部屋がカビ臭くなる
そもそも、カビ自体は無臭といわれています。
臭いの原因となるのが、カビが生成する物質や、カビが餌にする物質がカビの作用によって、変化して発生す場合がほとんどです。
つまり、床下でカビが繁殖を繰り返し行う過程で、臭いの原因物質が生成されているということです。
これらは、床下に広く充満し、やがて床上の部屋にまで侵入してきます。
その結果、部屋にはカビが生えていないのに、何だかカビ臭いといったケースが生まれるのです。
このような状態を防ぐには、臭いを生み出す根本である、カビの除去を徹底的に行うほかありません。
3.建物の老朽化やシロアリ被害の原因に
カビは建物の木材を腐朽させてしまうこともあります。
木材が腐朽すると建物全体の強度が低下するので大変危険です。
また、住宅がカビの被害を受けている場合、同時に「木材腐朽菌」の存在も危惧した方が良いでしょう。
木材腐朽菌は、その名の通り、木材を腐らせる菌のことです。
木材の主成分であるセルロース、ヘミセルロース、リグニンを分解し、繁殖すればするほど木材は腐り、建物の強度は低下してしまいます。
また、シロアリの存在も大変危険です。
シロアリは主な主食を木材としており、床下の基礎部分の木材を食い荒らし、耐久値を低下させてしまいます。
カビとシロアリの関係
カビとシロアリは一見、あまり関係がないようにも思われますが、実は密接な関係があります。
そのため、カビシロアリは、共存することで相乗効果をもたらすことがあります。
カビが木材に侵入すると、木材の強度が低下し、白アリの攻撃を受けやすくなります。
白アリは木材を摂食し、その際に周囲に排泄物や唾液を巻き散らかします。
それが結果として、湿度を高め、カビにとって最適な繁殖環境となってしまうのです。
このような相互作用があるため、カビとシロアリは同時に住宅に被害をもたらす場合があります。
床下のカビは自分で除去できるの?

床下のカビによる被害は誰にでも起こり得る現状です。
その被害には、さまざまなものがあり、中には重症化するケースもあります。
床下のカビが発覚した場合は一刻も早く対処する必要があるでしょう。
さて、ここでの議題ですが、カビの除去を自力で行うことは可能なのでしょうか?
「あまり費用を掛けたくない」「業者に依頼するのは抵抗がある」という方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。
結論から言うと、カビの除去を自力で行うことは非常に困難だと思われます。
では、実際にどのような理由から、自力での対処が困難だといわれるのでしょうか?
1.時間・労力がかかる
床下でカビへの対処を行うには、それなりの時間が必要になります。
さらに、床板の下で作業を行うわけですから、高さもないため、当然座ることもできません。
常にうつ伏せの状態で床下内を匍匐前進で移動し、作業を行う必要があります。
専門的に行っている業者でさえ、床下で作業を行うことは決して容易なことではありません。
また、比較的、住宅の面積が小さい場合でも、間取りによって基礎が曲がりくねっている場合があり、
自由に移動することもままならない場合もあります。
2.専門的な知識・技術が必要になる
作業を行うには、専門的な知識と技術が必要になります。
前文でも述べたように、カビの発生・繫殖にはさまざまなメカニズムがあります。
当然、それらを除去するのに対して、科学的な知識や確かな技術力が必要になります。
それらを持ち合わせていない状態で、見よう見まねで作業を行ってしまった場合、
より状態を悪化させてしまうケースもあります。
3.市販の薬剤では対応できない場合がある
カビの除去を行うには、専用の薬剤が必要になります。
市販でも、カビ除去用の薬剤は販売されていますが、業務用のものとは異なり、効果が薄い可能性があります。
また、薬剤の種類も数多く存在しており、その状況に合わせた薬剤を選択する必要もあります。
たとえ、効果のある薬剤を選択できていたとしても、作業の手順が不十分であれば、薬剤の効果が期待できない場合もあります。
4.根本的な原因箇所を特定できない可能性
作業に慣れていない方が除去を行う場合、カビの根本的な原因箇所を特定することができずに、再発を繰り返してしまうといったリスクもあります。
カビの発生となる原因は、環境、設備によってもさまざまですが、その原因箇所を特定することが何より肝心だということがいえます。
その点、専門業者が作業を行う場合は、原因箇所を特定し、確実にカビの除去を行うことができます。
再発のリスクの観点からも、カビの除去は自力で行うことはあまり、おすすめはできません。
業者が来るまでにできる床下カビの応急処置
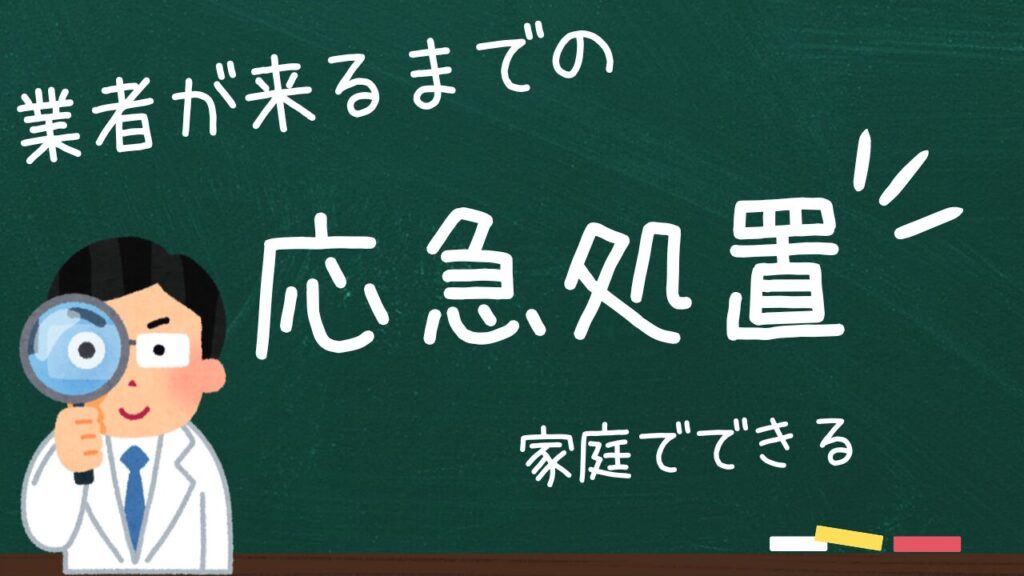
業者に依頼してから、実際に作業を行う日時まで余裕がある場合、応急処置を行っておくことで、これ以上被害の状態を悪化させないように防ぐことが可能です。
排水を行う
カビは、湿度が高い状態で、より活発に活動します。
そのため、床下に水が溜まっている状態の場合、排水作業を行っておくことで、高湿状態を避けることにも繋がり、結果的にカビの成長スピードを緩めることができます。
排水作業を行う場合は、点検口からバケツなどの容器を用いて水を掬って排出するほか、
排水ポンプなどを使用することで床下の水を排出することができます。
送風機を設置する
カビの除去をしてもいないのに、乾燥しても大丈夫なの?という意見も聞こえてきそうですが、
あくまで、これは業者が来るまでの応急処置です。床下に送風機を設置することで、乾燥を促すことができます。
そのため、カビそのものの除去ではなく、これ以上カビが広がってしまわないようにするための一時的な処理にすぎません。
とにかく、床下が湿った状態(高湿な状態)を避けるために、床下に送風機を設置することで、乾燥を促すことができます。
水災害時の保険と公的支援については、こちらの記事でも詳しく解説していますのでご参考ください。
↓ ↓ ↓
専門業者に依頼する際のポイント

床下カビの除去の経験(実績)が豊富
床下のカビの除去を専門業者に依頼する際は、経験(実績)が豊富な業者に依頼するようにしましょう。
通常のカビの除去と、床下のカビの除去は大きく異なります。
行動範囲も制限されるほか、床上よりも視野が狭まる為、床下の作業に不慣れな業者に依頼してしまうと、見えにくいカビの箇所を見逃してしまったり、最悪の場合、そもそも完全にカビを除去することができないといった可能性もあり得ます。
また、カビの除去に関する知識が不十分の業者が作業を行ってしまった場合は、カビによる被害を、より広げてしまうといったケースもあります。
防カビ施工・再発防止策を考案してくれる
カビの除去が終わったからといって、再度カビが発生する可能がないわけではありません。
その際に有効なのが、防カビ処理です。
基本的な防カビ処理は、カビの除去が終わった後に、防カビ効果がある薬剤で、再度コーティングを行うことで、カビの再発を防ぐことができます。
そのため、カビの除去~防カビまで、一括で依頼するのがベストだといえるでしょう。
また、カビの発生原因を特定したうえで、再発防止策を講じてくれる、アフターフォローが充実した業者に依頼することが大切です。
~まとめ~
床下カビは、健康被害や建物の構造劣化など、様々なリスクをもたらす存在です。
健康被害としては、カビの胞子を吸い込むことで引き起こされるアレルギー疾患や感染症などが挙げられます。
特に、免疫力の弱い、小さいお子さんがいるご家庭では、注意が必要です。
建物の構造劣化としては、床下の木材が腐朽し、建物の強度が低下してしまうことが挙げられます。
シロアリ被害にもつながり、最悪の場合、建物の倒壊という危険性も考えられます。
こうしたリスクを防ぐためには、床下カビの発生を抑制する対策が必要です。
床下カビは目に見えない場所が発生するため、放置してしまうと被害が拡大してしまう可能性があります。
定期的な点検と適切な対策を行い、健康被害や建物の構造劣化を防ぎましょう。
もし、床下カビが発生してしまった場合は、専門業者に相談することをおすすめします。
専門業者に依頼する際は、依頼するときのポイントを事前に把握しておくことも重要です。。
床下カビは、決して他人事ではありません。
自分の住んでいる家の床下環境を意識し、適切な対策を講じて、健康と安全な暮らしを守りましょう。


 2025.1.25
2025.1.25